相続時精算課税制度は、現在注目されている法制度である。
この制度を利用した親子間の財産贈与における一般的なトラブルについて紹介し、あらかじめ対策できるようにしておおこう。
この記事を読むことで相続時精算課税制度についての一般知識は網羅できるように書くので最後まで読んでいってほしい。
相続時精算課税制度とは?制度ができることによるメリット
相続時精算課税制度は、現行の法律において、60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子供や孫への贈与に対して、贈与者と受取人の組み合わせごとに選択できる制度である。贈与額が2,500万円以下の場合、特別控除により実質的に贈与税がかからず、それを超える贈与に対しては20%の税率が適用される。
わかりやすく説明していく。
まずは、この制度ができた背景。
たとえば、3500万円の財産を持っている乙さんという人がいたとする。この乙さんの子どもが自宅を購入することになったので、頭金として1000万円を贈与してあげたいと考えた。しかし1000万円も贈与した場合には、177万も贈与税がかかってしまう。せっかく、少しでも足しにしてほしいのに、こんなに税金かかってしまっては贈与も断念するしかない。
このような時のためにできたのが相続時精算課税制度。2500万円までは、贈与税を払わずにお金を渡すことができる。
ただし、2つの条件付。
①2500万円は相続されたものとみなし、相続が発生する際に加算して相続税の計算が行われる
②暦年贈与をすることができなくなる
要するに、2500万円の前借りができる仕組みなのだ。
だから、相続財産の総額が相続税の基礎控除3600万円を超えないと見込める場合は、相続時精算課税制度が有効になる。
この制度の特徴は、親や祖父母が相続を開始した際、これまでに受けた贈与を相続財産に加算し、相続税を計算した後に贈与税を差し引くことができることである。生前贈与には、暦年贈与と相続時精算課税制度2つの方法があるが、相続時精算課税制度を一度選択すると、あとから暦年贈与に変更することができないので注意が必要だ。
しかしながら、この制度に関連して税務上の問題が多発しており、裁判事例でも、贈与者が自発的に贈与税の届出や申告を行い、後で相続人が相続税の計算時に誤りが指摘されるケースが見らている。
相続時精算課税制度のトラブル事例3つ
ここからは相続時精算課税制度においてのトラブル事例を3つ紹介する。
①暦年贈与と相続時精算課税制度のどちらにするかで意見が別れた
贈与を行う理由として多いのが、「税金対策」である。生前贈与の制度を利用することで、最終的に払わなくてはいけない税額を減らすことができる。
生前対策のための制度として主に暦年贈与と相続時精算課税制度がある。それぞれの特徴は以下である。
◆暦年贈与:1人あたり毎年110万円ずつ贈与できる。贈与税はかからず、最終的に相続税の対象になる総額からひかれていく。そのため、相続税対策になる
◆相続時精算課税制度:2500万円までは非課税で贈与可能。ただし、相続時に精算する必要があるため、相続税対策にはならない。贈与した金額を持戻した相続税の計算になる。
一見すると、相続時精算課税制度は一度に多くの贈与ができるため、相続税対策になると勘違いしてしまう人もいる。しかし、相続税対策をしたいのならば、暦年贈与で財産総額を地道に減らしていく必要があるのだ。
そのことがわからずに贈与についての議論が白熱してしまい、口論になってしまうことがある。
このようなトラブルを避けるためには、暦年贈与と相続時精算課税制度の違いを理解し、被相続人・相続人の間で同じ認識を持っておくことが重要である。
②不平等な配分で贈与したせいで相続人の仲がわるくなってしまった
相続時精算課税制度は一度に大きな金額を贈与することができる。しかしながら、これには不平等な相続になってしまう危険性をはらんでいる。
例えば、相続財産の総額が3000万円であったとして、子Aさんの自宅の購入のために2000万円の贈与をしたとする。これがあとになって、別の兄弟である子Bさんが「ずるい!」と言い出すことがあるかもしれいない。
現に、この贈与は「特別受益」にあたる可能性が高く、自宅資金をもらった子Aさんは相続の際になにももらえないことになってしまうかもしれない。このとき子Aさんと子Bさんがもらえる相続の割合について主張が食い違い、仲がわるくなってしまうケースもあるのだ。
このような事態を避けるためには、安易に贈与をすることがないように注意し、相続人同士が公平に遺産をもらうことになるか?ということを考える必要がある。
事例概要
この件は、平成27年に始まった相続税の申告において、相続人が、平成18年から21年にかけて被相続人から受けた財産を相続財産に含めるべきかどうかが争点となった事例です。税務署は、被相続人からの贈与(現金や建物)が、被相続人自身によって相続時精算課税制度に関して申告されていたため、相続財産に含まれるべきと主張しました。しかしながら、相続人は被相続人が自分の承諾なしに申告書を作成し提出したため、その申告は無効であると反論しました。
法廷の判決
法廷は、まず、納税者本人が申告書を提出することが求められている原則を示し、「納税者以外の者が、本人の許可なく納税者の申告書を作成し提出した場合、その納税申告は無効である」という考え方を提示しました。次に、法廷は、納税者以外の者が申告書を作成し提出した場合でも、有効となる場合を、「その者が、納税者から明示的または暗示的に申告行為を行う権限を与えられている場合」と述べました。
この特定の事例では、被相続人が申告手続きを行ったことが明らかであったため、法廷は、相続人が被相続人に対し、「申告書に関する申告行為を行う権限を与えていたと判断できるかどうか」について検討し、次の事実関係を指摘しました:
① 相続人は、建物の贈与に関する登記手続きを被相続人に任せていた。
② 後の年の課税申告書を作成する際、農協などでの相談時に、必要な書類の提示などの対応は被相続人が行っていた。
③ 課税資金は被相続人が支払っていた。
④ 相続人の印鑑は被相続人も使用できる状況であった。
⑤ 相続人が申告手続きなどの必要な手続きを積極的に行っていなかった。
⑥ 後の課税申告において、相続人は贈与税の払い戻し金などの振込みを認識できた。
⑦ 被相続人が相続人の口座から払い戻し金を引き出した際に異議を申し立てなかった。
このような事実から、法廷は、一連の手続きに関して、相続人が「被相続人に包括的に委任していたと判断できるため、精算課税申告についても、被相続人が申告行為を行う権限を明示的または暗示的に与えていたと判断した。
まとめ
この種の問題の原因は、被相続人と相続人のコミュニケーション不足なのか、それとも他の要因が影響しているのかは明確ではない。将来の相続税にも影響を与えないよう、生前贈与の財産移転は、関係者間での明確な合意のもと、専門家のアドバイスを受けながら実施することが重要。

弁護士費用について詳しく解説したので読んでみてくれ
-1-300x169.png)
-1-300x169.png)
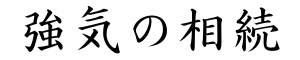
-3.png)

-63-300x169.png)
-62-300x169.png)
-61-300x169.png)
-60-300x169.png)
-59-300x169.png)
-55-300x169.png)
-58-300x169.png)