被相続人が認知症の場合、遺言書の効力が争われ、相続トラブルが発生しやすくなります。相続人が認知症の場合、遺産分割の協議が進まない可能性があり、相続放棄すら自己判断できないことがあります。認知症になる前に、遺言書の作成に対処することが重要です。相続人に強度の認知症の方が含まれている場合は、成年後見人を指名して遺産分割協議を進める必要があります。

親族に認知症がいる家族は要注意だ!
被相続人と認知症
契約や売買などの取引を行うには、判断能力(意思能力とも呼ばれる)が必要です。認知症や加齢により必要な判断能力が欠如している場合、契約が本人の真意に基づいているかどうかが問題になります。たとえば、被相続人の預金が生前にその本人のカードで引き出された場合などが挙げられます。
被相続人が自らの意思で引き出したものか、それとも同居の親族が不正に引き出したものかといった争いが生じる可能性があります。相続においても、同様に判断能力の不足が原因でトラブルが発生することがあります。遺言書の作成を前提とした認知症と相続トラブルに焦点を当て、認知症になった関係者がもたらす問題やその対処法について簡単に紹介したいと考えています。



相続人の関係については以下の記事を読んで理解してくれ
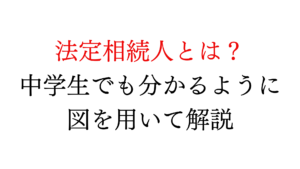
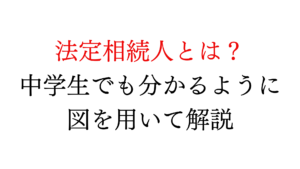
被相続人が遺言書を作成する際に認知症などの状態である場合の問題点
遺言能力
15歳に達すると、遺言を作成することが可能ですが、その際には必要な判断能力(遺言能力とも呼ばれます)が欠かせません。この能力の不足が生じる典型的な状態の一つが認知症です。
成年後見人による遺言書の作成には、判断能力が一時的に回復した場合でも、医師2名の立ち会いのもとで厳格な手続きが求められます。成年後見制度は、認知症などにより判断能力が低下した個人を保護し、サポートするための制度です。
深刻な認知症の場合、その個人は遺言能力を有していない可能性が高く、認知症の状態で有効な遺言書を作成することは難しいです。
遺言の無効確認訴訟
遺言の無効確認訴訟は、遺言が無効であることを確認するための法的手続きです。例えば、「被相続人が遺言書を作成する際に認知症であり、遺言能力がなかった」といった論争が典型的な例です。遺言が無効であると確認されれば、その遺言は無効と見なされます。裁判の際には、遺言能力の有無について裁判所が複数の要素を総合的に考慮して判断します。また、被相続人が存命中においては、遺言無効確認の訴えは却下されることがあります。
遺言書作成時に作成者の認知症が疑われる状況では、相続人などが遺言書の存在を知っていたとしても、不安な状況が続く可能性があります。
遺言書作成時の留意点
元気な状態で遺言書を作成する
不安や論争を未然に防ぐためには、遺言能力が確認される段階で遺言書を作成することが不可欠です。遺言能力が異論の余地なく認められる時期が理想的であり、基本的には認知症の兆候が見受けられない段階で、年齢的にも若い方が安心です。
遺言の方法や種類を検討して適切なものを選ぶ
遺言書を作成する際には、遺言能力を立証する証拠を事前に用意することが重要です。
遺言書の作成には複数の方法や種類が存在し、それぞれの特徴を理解し、選択後にはそれに応じた対処を行うことが望ましいです。一般的に利用される遺言の方式には、公正証書遺言と自筆証書遺言があります。
公正証書遺言の作成について
遺言能力を確認するために、公正証書遺言を利用することは一つの手段です。ただし、公正証書遺言においても、必ずしも遺言能力があったと認められるわけではありません。一般的に言えることは、公正証書遺言は自筆証書遺言よりも遺言能力を立証するための証拠として強力であり、次に述べる「自筆証書遺言」に比べて無効とされることは少ないとされています。ただし、公正証書遺言の作成には所定の費用、手続き、時間がかかります。
自筆証書遺言の作成について
遺言内容を柔軟に変更する可能性が高い場合や、急いで簡潔な内容の遺言を作成したいといった理由から、ますは自筆証書遺言を作成することが求められることがあります。これ自体は適切な選択肢であるが、自筆証書遺言の場合は公正証書遺言よりも無効とされる可能性が高まり、必要に応じて不足を補うための対策が必要です。特に、認知症などが遺言能力に疑念を抱かせる場合、遺言書作成直前の医師の診断書(認知症の疑いがない旨の)を用意するなどの対策が考えられます。
また、比較的費用がかからないため、法務局による自筆証書遺言保管制度の利用も検討してみましょう。
認知症のある相続人が遺言執行時に生じる問題
相続人が認知症などの理由で判断能力を失った場合、相続トラブルが発生する可能性があります。遺言書を作成する際には、こうした相続トラブルを考慮し、遺言執行時に問題が生じないように慎重に配慮することが重要です。同時に、相続人には成年後見などの必要な手続きを活用するように促しましょう。
遺言書作成により遺産分割を回避する
遺産分割協議を行う際には、認知症を含む相続人全員の同意が必要です。認知症等により判断能力が低下して同意が得られない場合、成年後見などの手続きが不可欠です。遺産分割調停や審判手続きも同様です。従って、認知症等の相続人がいる場合、通常よりも遺産分割協議や同調停・審判が長期にわたる可能性があります。
一方で、遺産分割が不要な場合、手続きに巻き込まれずに相続財産の帰属を円滑に確定させ、遺言執行手続きを進めることができます。遺言書を作成する際には、専門家の関与を通じて遺産分割を回避できないかどうかを検討することが望ましいでしょう。
遺言執行者の指定には専門家を選ぶことを検討する
遺言執行者の指名やその数、与えられる権限については様々な観点が存在しますので、弁護士との綿密な相談が重要です。ただし、専門家が遺言執行者である場合、相続人が認知症などで手続きが難しい場合でも、成年後見人の選任手続きなど必要な業務を円滑に進めていくことが期待できます。
なお、指定された遺言執行者が死亡や他の理由により就任できない場合も考えられますので、そのようなリスクを低減させるためには、可能性の低い弁護士を指定するか、複数の弁護士を指定することが望ましいです。
成年後見制度などの活用を考慮する
遺贈においては、受遺者が承認または放棄の権利を持っています。しかしこれらの権利を行使するためには、受遺者が必要な判断能力を有していない場合、成年後見などの手続きが必要です。同様に、相続人が相続放棄の手続きを行う場合も同様です。相続人に認知症等の方がいる場合、事前に成年後見制度などの活用を検討することで相続トラブルを回避する可能性が高まります。
相続とは別に、判断能力が著しく低下した方には、本人の財産を守るためにも各種後見制度の早期活用が必要です。また、そのような状態に陥る前からの対策として、任意後見契約やホームロイヤー契約など、高齢社会に適した法的サポートシステムが整備されています。早い段階で自身に合ったサービスを検討することが望ましいです。
まとめ|信託の有効活用
また、遺志を具現化するためには、民事信託契約を活用する方法もあります。民事信託は、被相続人が生前かつ判断能力がある段階で、主要な財産の帰属先を事前に定める機能があります。さらに、遺言で認められない後継ぎ遺贈(次の次の遺産の帰属先を指定)など、信託には民法上の遺言にはない利点が存在します。最適な方法は何か、ご希望に合った結果を得るためには、両方向から詳細な説明を受け、経験豊富な弁護士に相談されることが良いでしょう。



弁護士費用について知りたいなら以下の記事を参照!
-1-300x169.png)
-1-300x169.png)
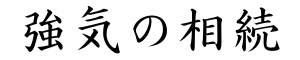
-4.png)

-63-300x169.png)
-62-300x169.png)
-61-300x169.png)
-60-300x169.png)
-59-300x169.png)
-55-300x169.png)
-58-300x169.png)